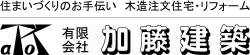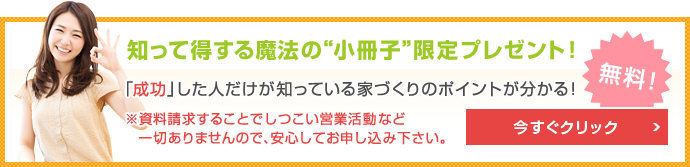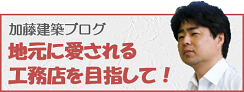1)耐震規定の変遷
耐震基準は大きな地震の度に研究がすすめられ、規定化されてきました。
現行基準は1981年(昭和56年)の大改正と、2000年(平成12年)の接合部規定・バランス規定追加によって、耐震性が大きく向上しています。
このため、1981年以前の木造住宅は、特に耐震補強の促進が叫ばれ、地域によっては補助金が出るようになっています。
そのあと2000年(平成12年)までに建てられた住宅も、耐力壁の量は十分であっても接合部の緊結が不十分な場合があり、できるだけ耐震診断を受けるよう勧められています。
■1950年(昭和25年) 建築基準法制定
構造基準ができた
・壁量規定
・筋交いをボルト・かすがい・釘等で、柱はかすがいで止める
・耐力壁はつり合い良く配置(計算式無し)

※単位面積当たりの必要壁量
■1959年(昭和34年) 建築基準法改正
・必要壁量増加
・柱や梁の太さなどを規定

■1971年(昭和46年) 建築基準法改正
・基礎はコンクリートまたは鉄筋コンクリート布基礎

■1978年(昭和53年) 宮城県沖地震 最大震度5
■1981年(昭和56年) 建築基準法大改正 一般に「新耐震基準」
・必要壁量の増加
・面材(合板等)耐力壁を規定
・基礎は原則鉄筋コンクリート
※57年から、公庫標準仕様に筋違いプレート(30×90用)が規定される

■1995年(平成7年) 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災) 最大震度7
■2000年(平成12年) 建築基準法改正
・地帯力に応じた基礎構造(地盤調査が原則必要に)
・筋違いサイズによる金物規定
・引抜き力による柱頭柱脚金物の規定(N値計算)
・耐力壁の配置バランスの計算法が規定(4分割法・偏心率)

現行基準は1981年(昭和56年)の大改正と、2000年(平成12年)の接合部規定・バランス規定追加によって、耐震性が大きく向上しています。
このため、1981年以前の木造住宅は、特に耐震補強の促進が叫ばれ、地域によっては補助金が出るようになっています。
そのあと2000年(平成12年)までに建てられた住宅も、耐力壁の量は十分であっても接合部の緊結が不十分な場合があり、できるだけ耐震診断を受けるよう勧められています。
■1950年(昭和25年) 建築基準法制定
構造基準ができた
・壁量規定
・筋交いをボルト・かすがい・釘等で、柱はかすがいで止める
・耐力壁はつり合い良く配置(計算式無し)

※単位面積当たりの必要壁量
■1959年(昭和34年) 建築基準法改正
・必要壁量増加
・柱や梁の太さなどを規定

■1971年(昭和46年) 建築基準法改正
・基礎はコンクリートまたは鉄筋コンクリート布基礎

■1978年(昭和53年) 宮城県沖地震 最大震度5
■1981年(昭和56年) 建築基準法大改正 一般に「新耐震基準」
・必要壁量の増加
・面材(合板等)耐力壁を規定
・基礎は原則鉄筋コンクリート
※57年から、公庫標準仕様に筋違いプレート(30×90用)が規定される

■1995年(平成7年) 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災) 最大震度7
■2000年(平成12年) 建築基準法改正
・地帯力に応じた基礎構造(地盤調査が原則必要に)
・筋違いサイズによる金物規定
・引抜き力による柱頭柱脚金物の規定(N値計算)
・耐力壁の配置バランスの計算法が規定(4分割法・偏心率)

| ~1981年5月 | 1981年6月~2000年5月 | 2000年6月~ |
|---|---|---|
| 基準を守った家屋の被害が甚大・・・! →大地震のたびに強化上昇 | 宮城県沖地震を反映し・必要耐力壁量増加・筋かい金物規定 ・原則鉄筋コンクリート基礎 | 兵庫県南部地震を反映し・強さに応じた柱頭柱脚金物規定 ・耐力壁の配置バランスの規定 |
| 揺れに耐える壁を増やし、基礎が壊れないようにした。 | 壁が強い分、柱が抜けてしまうのを防ぐとともに、配置バランスを計算式で規定した。 |